「実験って難しそう…」「失敗ばかりで自信がない…」
そんな風に思っていませんか? 実験は、科学の基礎となる重要なプロセスですが、初心者にとっては戸惑うことだらけかもしれません。 特に、大学での実験実習や研究室に配属されたばかりの頃は、わからないことや不安なことがたくさんあるでしょう。
この記事では、10年以上の実験経験を持つ大学教員が、初心者が意識すべき実験のコツを丁寧に解説します。 具体的な実験手順ではなく、実験に対する考え方や心構えを中心にご紹介します。
- 実験前に何を準備すべき?
- 失敗しないためのコツは?
- 実験結果をどう解釈すればいい?
これらの疑問に答えるとともに、実験を成功させるためのヒントをお伝えします。 この記事を読めば、実験に対する不安が解消され、積極的に取り組めるようになるはずです。ぜひ最後まで読んで、実験スキルを向上させましょう!
計画編
研究では答えが分かっていない事を調べる
研究では答えが分かっていない事を調べます
どのような実験をすれば答えが分かるかは、自分で考える必要があります
答えが分かる or 答えに近づけるような実験デザインにしましょう
実験ではコントロール (対照群) が大事
実験ではコントロール (対照群) が非常に大事です
実験は「何を何と比較するのか」が重要です
比較相手 (コントロール) の設定がイマイチだと、苦労した実験群のデータも活きません
コントロールのデータがきちんとしていれば、少なくとも実験系に問題がないことも分かります
どんな些細な実験でもコントロールを大事にしましょう
研究・実験では誰も答えを知らないかも
研究・実験では、教員も答えを知っているとは限りません
むしろ、誰も答えを知らないことを明らかにするのが研究であり、そのために実験を行います
なので、学生の質問・相談に対しては、解答ではなく助言 (例 自分ならこうしてみる) をする場面も多いです (ごめんね)
「誰も調べたことがない」は研究する理由にならない
研究は「誰も調べたことがない」ことを調べるものですが、「誰も調べたことがない」自体は研究する理由になりません
実際は、とりあえず実験をやってみたら面白い結果が出ることもあります
その場合でも、やる前に以下の点を考えてみましょう
・予想される結果とやる意義
・誰も調べていない理由
例) 東京タワーのてっぺんから卵をばらまいたらどうなるか
・予想される結果とやる意義
→卵が地面に落ちる、めちゃくちゃ怒られる、東京タワーから卵をばらまいてはいけないことが分かる
・誰も調べていない理由
→有益な情報が得られない、危ない、卵がもったいない
教わる・教える
実験技術を獲得する最良の方法は人に習うこと
実験技術を獲得する最良の方法は、その技術を持っている人に習うことです
本を読むor動画を見るより、圧倒的に効率的に習得することができます
まずは自分の周囲でその技術を持っている人を探してみましょう
いない時は、持っている人を知っていそうな人にきいてみましょう
師匠のやり方を完全に真似する
何かを教わる時は、師匠のやり方を完全に真似しましょう
「前の職場 (ラボ) のやり方は…だった」からといきなりアレンジを加えると、失敗時のトラブルシューティングが難しくなります
オリジナリティを出すのは師匠の再現ができてから
型を覚えずに型破りを目指すと形無しになります
実験を教える時はプロトコルを渡す
実験を教える時は手書きでも良いからプロトコルを渡しましょう
・口頭で全てを説明・理解するのは困難
・予習・復習が容易
・教わる側は口頭説明に集中できる
・教える側の負担も減る
苦労して作ったプロトコルを渡すのに抵抗があるかもですが、自分がした苦労を後続にさせないのが良い大人です
実験や作業を教える時は見習い期間を設ける
ルーチンの実験や作業を教える時は、見習い期間を設けるのがおすすめ
見習い期間は文字通り、ただ作業を見ているだけの期間のことです
教える側は説明をしなくて良いのでコストがかなり小さいです
見習い期間で全体像を把握してからの説明すると、
・教わる側の理解度が高い
・教える側の負担も小さい
「門前の小僧習わぬ経を読む」というやつです
教えることは大なり小なりコストがかかる
教えることは大なり小なりコストがかかります
ルーチンの実験も、教えながらフルパフォーマンスを出すことはできません
時間・手間・体力・集中力などのコストがかかります
教える側は、時間・準備・人員に余裕をもって教えましょう
教わる側は、教える側がコストを払っていることに感謝して、全力で教わりましょう
意図・行動・期限を説明する
指示をするときは意図・行動・期限を説明しましょう
説明なしで的外れなことをするとお互いに不幸です
逆に、説明なしの指示をされた場合は自分で宣言しましょう
例)
教員:「Aの実験を時間がある時にやっておいて」
学生:「Bの実験結果の裏付けを取る意図と理解しました。今週末までに結果を出します」
もし意図の理解や期限設定がズレていれば、宣言時に指摘されます
情報は客観的な指標で共有
情報は可能な限り客観的な指標 (数値など) で共有しましょう
例) 試薬の残量が「ほとんどありません」
→「100 ml 程度です」、「ボトル半分です」
主観的な情報伝達は誤解を招きます
可能な限り、万人に共有される指標を使って情報伝達しましょう
練習・本番編
スマホで写真を撮る
実験時にはスマホで写真を撮りまくりましょう
・試薬の型番・ロット番号
・実験器具やその配置
などを全てメモするのは困難です
スマホで写真を撮っておけば
・多くの情報量を
・正確に
・視覚的に
記録できます
日付情報も残るので、さかのぼって調べるのも容易です
まずは1人で練習できるようになることを目指す
難しい技術を学ぶ時は、まずは1人で練習できるようになることを目指しましょう
難しい技術の習得には練習が必要です
練習する時にも誰かの指導が必要だと、練習のハードルが高くなり習得まで時間がかかります
まずは1人で練習するための技術や環境を揃えましょう
1人で練習できるようになったら、たまに師匠からチェックを貰いつつ、ひたすら練習あるのみです
プロトコルに従う
初めての実験は可能な限りプロトコル通りに行いましょう
アレンジを加えて失敗したら…
①結局プロトコル通りにやり直す
②「この実験は難しい、私にはできない、もうしない!」
アレンジを加えても成功すれば良いのですが、失敗すれば結局レシピ通りにやり直すことになります
多くの場合は、最初からプロトコル通りにやるのが近道な印象です
実験と料理は似ている
実験と料理は「プロトコルに従うのが大事」という点で似ています
両者を失敗する原因は下記など
・指示されていることをやらない
・指示されていないことを勝手にやる
・試薬 (食材、調味料) を別のもので代用する
オリジナリティを出すのは下記を達成してからにしましょう
・プロトコルを完全に再現できる
・プロトコルの意味・意図を完全に理解している
実験のステップの意味を考える
実験する時は各ステップの意味を考えましょう
機械的に「①→②→③→…の手順で実験する」と思い込んでいると、
・予期せぬトラブルに対応できない
・より良い方法を思いつかない
たまに以下のような事を考えてみましょう
・②のステップは必須なのか? スキップしたらどのような問題が起こるのか?
・なぜ①の次に②を行うのか? ①→③→②の順ではダメなのか?
全ての手順の意味・意義が分かるとは限りませんが、考える習慣を持つことは大事です
ルールにないこと ≠ やっていいこと
ルールにないことは何でもやっていいわけではありません
例えば、
共有の実験機器を自由に使いたい
→予約についてのルールがないので毎日朝から晩まで予約する
→予約時間や回数についての新たなルールができる
→全ユーザーに影響
本当に必要ならば (担当者に相談するなどして) 実施を検討すべきですが、不必要に権利を主張・行使することはやめましょう
道理が引っ込まないかぎり無理は通りません
練習は本番のように、本番は本番のように
私が恩師に教わったことに「練習は本番のように、本番は本番のように」というのがあります。
練習は繰り返し行なえます
本番を想定して、本番でベストパフォーマンスを出せるように繰り返し練習しましょう
本番は次を想定しません
どんなトラブルが起こっても、その本番でベストが出せるようにあがきましょう
本番の実験でしか学べない事もある
「本番の実験でしか学べない事もあります」、これも恩師の教えです。
どんなに本番を意識した練習でも、やはり本番とは違います
本番でしか学べない事は多いです
例) 緊張感、プレッシャー、環境、道具、トラブル対応
本番の機会は多く得て、多くを学びましょう
トイレが近い人は実験前に餅・団子を食べる
トイレが近い人は実験前に餅・団子を食べるという手があります
確かにトイレに行く間隔が長くなる気がします(個人の意見)
すぐにトイレに行くのが難しい仕事・実験・バス移動などにも使えます
我慢しないのが最良の方法ですが、おまじないの1つとして
解釈編
ネガティブな結果は失敗ではない
ネガティブな結果が出るのは失敗ではありません
・ポジティブともネガティブとも言えない結果が出ること
・そのような結果が出る実験をデザインすること
が失敗です
ネガティブな結果は「その方法ではうまくいかない」と分かったということです
その結果をもとに次に進めるので、ある意味成功です
原因なのか結果なのかを考える
観察された事象が原因なのか結果なのかは考えましょう
例) お金持ちはマイホームを持っている
原因:マイホームを買ったからお金持ちになった
結果:お金があるからマイホームを買った
上は簡単な例 (多分後者) ですが、原因 or 結果の判断が難しい・できない実験や研究は多々あります
思い込みに注意してよく考えましょう
実験の成否が分かる指標を把握しておく
実験の成否が分かる指標を知っていることは大事です
実験結果が期待と違った
→実験自体が失敗した可能性があるが、それを評価するための指標を知らない
→再実験 (最初に戻る)
まずは実験の成功を確認できる指標を見つけましょう。もっと正確に言えば、実験を終えてからその指標を探すのではなく、成功を確認できる指標が得られるような実験を予めデザインしておきましょう
実験結果の解釈は、実験の成功を確認できてからです
おすすめのモノ編
パール ピュア200のメガネのくもり止め
パール ピュア200のメガネのくもり止めはおすすめ
価格もお手頃で、梅雨の時期のメガネユーザーの強い味方
メガネに直接垂らしてティッシュで延ばして拭き取るだけで使えます
実験の防護ゴーグルにも使えます
USB延長ケーブル
高価な実験機器にはUSB延長ケーブルをつなぎましょう
USBを直に抜き差しする場合、差し込み口が壊れる可能性あり
→機器の動作は正常なのに高額な修理費用が必要、最悪使用不可になるかも
延長ケーブルを常時つないでおけば、安価でリスク回避できます
布テープ付きのマスカー
大掃除での養生には「布テープ付きのマスカー」が超有用
テープを貼ってビニールを垂らすだけで養生完了です
45 Lビニール袋をハサミで切って、ガムテープで貼る作業はもう必要ありません
便利過ぎて、一度使うとコレなしの実験室の大掃除には戻れなくなります
是非一度お試しを
Amazonの時計付きスマートスピーカー (Echo Dot)
Amazonの時計付きスマートスピーカー (Echo Dot) はタイマーとして有用
・「アレクサ、タイマーを〇分に設定」と言えば、手がふさがっていてもタイマー設定ができます
・残り時間も表示される
ラボで実験タイマーとしても使いたいですが、絶対遊びたくなるので利用には注意を
実験室で使いたい小物については↓の記事もお読みください。
まとめ
この記事では、実験経験10年以上の大学教員が、初心者が意識すべき実験のコツを「計画」「教わる・教える」「練習・本番」「解釈」「おすすめのモノ」の5つの視点から解説しました。 実験は、単に手順をこなすだけでなく、目的を理解し、適切な準備と心構えを持つことが重要です。 この記事を参考に、実験に対する理解を深め、成功体験を積み重ねていきましょう。
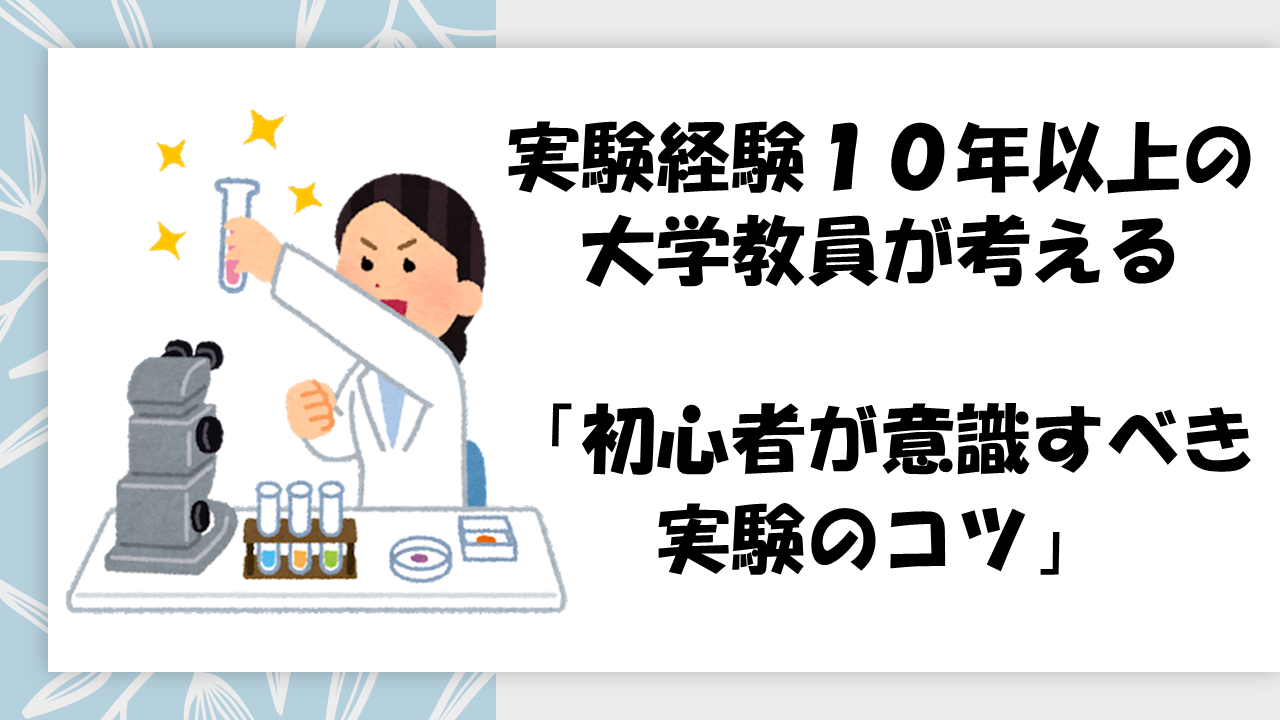























コメント